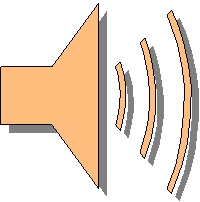司として,任ぜられていた。
贅を尽くした豪華な屋敷に住み、領地は、岡崎から知立に及ぶ,広大な土地を持ち、
東海道筋に知られた、比類なき裕福な長者であった。 だが、兼高夫妻にとって、
一つだけ淋しい,思いがあった。それは、二人の間に子宝が、なかったことである。
兼高はある日、鳳来寺の薬帥如来が、霊験あらかたであることを聞いた。
『わしわこれから、鳳来寺のお山へ、願かけに参る、そちも一緒に,付いて参られよ』
と妻に命じた。兼高夫妻は慌しく,身仕度をすると、矢作の宿を,出立するのであった。
鳳来山は,山ひだが重なり谷は深く、昼なお暗く、まことに霊気みなぎるお山であった。
『ブッポゥソゥー ブッポゥソゥー』とコノハズクの鳴き声までが,仏法僧と有り難い響
きに,聞こえた。
兼高夫妻は七日七夜、薬師堂に参籠して『南無,薬師如来さま,どうか子宝を,授けえ』
と,祈り続けた。満願の夜、祈り続ける二人の耳に
『そなた達の願いを、かなえて,とらせますぞ』と、薬師如来のお告げが,聞こえた。
ほどなくして奥方は身ごもり、珠のような姫が,誕生するのであった。
薬師如来は東方の、浄瑠璃浄土におわす,仏である,というこうから、姫の名もそれに
あやかって,浄留璃姫と、名付けられた。
その後、十六年の歳月が,流れて行った。東海の穏やかな気候と,父母の慈愛に育ま
れて成人した姫は、近隣諸国にも評判となるほどの,美しさであった。
また、姫が奏でる琴の音は浄瑠璃姫と,呼ばれるにふさわしく、夜明け前の空のよう
に、美しく澄みきっていた。
承安四年、西暦1174年の春が,巡ってくる。源氏の御曹子,牛若丸は、京都三条の
豪商金売り吉次に伴われ、ひそかに鞍馬山を下りて東海道を東に向かいつつあった。
平家全盛の,この時代、紗那王,と名乗って,鞍馬に潜んでいた牛若丸は、金売り吉次
の手引きで,奥州平泉に住む、藤原秀衡のもとを,頼ろうとしていたのである。
それは、『源氏再興』と言う一念を,心に秘めての、旅立ちであった。
牛若丸の一行は,尾張の国に人ると、熟田神宮の大官司、藤原季範の館に,一泊した。
ここは、兄となる頼朝の,母、由良御前の,屋敷である。
牛若丸はここで、自らの発意で元服し、源九郎義経と,名乗った。
当年とって十六歳、りりしき若武者の,誕生となるのであった。
熟田を出た一行は、やがて、矢作の宿の,兼高長者の屋敷へ人る。
『義経様、道中難儀でござった、ごゆるりと,お休み下され』と、
兼高夫妻は,義経一行を手厚く,もてなした。
静に更け行く春の夜、月の光が,庭一面の桜の花をおぼろに,照らしている。
どこからともなく笛の音が,びょうびょうと,流れてくる。義経が吹く名笛、『薄墨』の,調
べだ。亡き母、常盤御前の形見の名品を,春月に向かって吹いている。
その光りの中に,濡れながら浄瑠璃姫は、熱き想いを押さえて,たたずむ。
間もなく姫は当家に伝わる名琴,『松風』を引き寄せ、笛の音に合わせて,弾きはじ
めた。その名も『想夫恋』高く,低く,笛の音と琴の響きは、桜のあたりの夜気を、一層
なまめかしく盛り上げ、陰々と,溶け合っていた。
源氏の若君を、わが家に迎えたときから,浄瑠璃姫の胸に、生まれて初めての,熱い,
ときめきが、芽生えていた。義経の目と,目を見交わすたびに、姫の胸は高鳴るばか
りであった。義経もまた姫と,同じ想いである。
人気も消えた,丑三つ時姫は,沈香の枕を傾けて,長い黒髪を,錦の御座の上にな
びかせ伏せている。月光の薄明かりに、照らされた姫の姿は,弥勒菩薩の化身を,
思わる。その姿に、高まる義経の想いは,やる方なく、とうとう七重の御簾を巻き上
げ、そっと姫の寝所に、くぐり,人って行った。
『姫、姫、わしじゃ』
『ああ一、義経さま一』と、白魚のような腕で,義経は,引き寄せられる。
『十五夜の,月の人るさを待ちかねて、夢にや見んと、まどろむぞ君』
と姫は申しつつ、.二人は堅く,結ばれるのであった。
しかし、義経の思いと姫の思いは,つかの間の雫と終わる,運命にあったのである。
義経は大望の,ある身であった。源氏再興と言う使命が,名残惜しむ義経の心を,
堅く,戒めていた。
『別れ行く,思いを問うかこの宿の、花を惜しみて鳴くか、うぐいす』と、義経は,想い
を歌に託し『薄墨』の名笛を,形見として姫に与え、遠く奥州へと,下って行くので
あった。
浄瑠璃姫は泣く泣く矢作の里に,残された。
諸行無常の鐘の響きは、今を限りと身にしみて,聞こえてくる。
短い縁ではあったが姫は、義経のことが忘れられない。
別れの日から,日が経つに従い、一夜の思いがまざまざと蘇り、姫の胸を,熱く切な
く,かき.立てた。
金売り吉次に伴われた,義経の一行は、遠江を旅して,駿河の国に人る。
小夜の中山を越え、東海道の,三大難所の一つと言われた,越すに越されぬ大井
川を渡り,島田の宿に仮寝する。
明くる日は、蔦の細道の,宇津ノ谷峠を越えて,途中、手越の宿に馬を休めた。
そのとき吉次は、府中から伊豆ヘ下る道を,陸路を行くか,海路にするか,いずれを
とるか,思案にくれていた。
この先の,清見潟の関所越えが,難儀と,思われたからである。
『この度は,源氏の若君を連れている、万一のことがあっては……』と危慎した。
吉次は、義経の前に膝まづき
『御曹子、江尻の先の,清見潟の関所には,平家方の地侍が道をふさいで下りま
する。それ故、海路を進みたいが,天候が,荒れ模様で御座います。いかが致し
ましょうか』義経は,空を見上げながら。
『天候の荒れは,苦しゅうない。海路を行こうぞ』と決断を下した。
『船の,手配をせい!』吉次は供の者に指示した。
『はあっ、かしこまりました』と、その支度に,二、三の者がばらばらと駆け出して
いった。
ひと息ついた一行は、安倍川を渡り、大谷を経て,有度浜に出る。
暗雲漂い,波は大きく返していたが、風はあっても,さほどではない、間もなく、
有度山南麓の海岸から,舟を出した。
早くも義経の心は、兄の頼朝がいる,伊豆の,ひるケ小島に飛んでいた。
頼朝は、十三歳にして,平治の乱に参戦し、敗れて捕らえられたが、池の禅尼の
計らいで,命だけは助けられ、永暦元年、西暦1160年,この,ひるケ小島に,流され
ていた。
また、愛鷹山の麓にも,今は法師となって、全成と、名のる兄もいる。
この二人の兄に,会えるやも知れぬ、期待を抱いて義経は、船の行く手を見っめ
ていた。
船が一行を乗せて,三保の岬を過ぎたころ、突然、雷鳴がとどろき、一条の,青白き
光が走った。やがて,頬を打っ激しい雨と、強い風に見舞われたが船は、狩野川
の、河口を目指して進んだ。
だが、義経の期待を裏切るかのように、夜になると天候は,ますます荒れ狂った。
風雨は,一層の激しさを増し一行、十三人が乗った小船は天高く,突き上げられるか
と思えば奈落の底に,叩きつけられるように,もてあそばれた。
富士川から押し出る濁流に,行くてをはばまれ、擢も,流れてしまう。
供の者達は船底に,頭を伏せ、念仏を唱える者もいた。
そのとき義経は、稲妻の光で船の舳先に,白いものを見た。
『おい、何んだ,あれは』。
供の者が,一斉に顔を.』上げて,闇を透かして見る。誰かが叫んだ
『狐がいるぞ,白狐じゃないか』
『オッーこれは,稲荷大明神の使いの狐だ、船を導くために,神が,遣わしてくれた
のだ』と義経は言った。
鞍馬山で修業のおり、篤く信仰した,伏見稲荷大明神の神霊の,御加護であった。
船は,大時化によって,上下左右と激しく揉まれながらも,次第に陸地の方に,打ち
寄せられていった。絶壁のような,怒濤に巻き込まれた瞬間、ザザッーと船底が,
砂をかむ。
供の者は、海}に飛び降りると、満身の力で船を,浜辺に引き上げた。
砂丘の正面には,黒々とした松林が見える。そこはまさしく蒲原の、田子の浦吹き
上げの,浜であった。しばし松籟の音を聞きながら、一行は、松の根方に休ん
だが、次第に深い眠りに、落ちてしまうのであった。
半日は過ぎたであろうか、大勢の里人達が,物珍しそうに一行の顔を,のぞき込んで
いる。ざわざわとした話し声で、皆、目が覚めた。
『お主たちは、どこからおい出じゃ』
吉次は答えた。
『我らは,都より東へくだる冠者を,一人預って,旅をしている者である。ところで、
旅の疲れを癒すに,いずこか,休むところはないか』
里人が,導くままに一行は、松林を後にした。
目指す所は、東山台地の南にある,吹き上げの館であった。
五軒坂へ登る途中、傍らの窪地に,小さな湧水の池がある。
義経は側によると、池から清水を汲んで墨をすり、筆を執って,さらさらと紙に一筆,
したためた。
後ろ髪を引かれる思いで,別れてきた、恋しき浄瑠璃姫への,便りであった。
と、その時、姿を消していた白狐が,再び現れる。
義経の手から,一片の手紙を口にくわえると、白狐は,一目散に西へ向かって,かけ
て行った。
またもや、守護神の稲荷大明神が,義経の思いを浄瑠璃姫に伝えよと白狐を、遣
わしたのである。
義経は,西の方に同かい、静かに両手を合わせ,祈りを込めた。
時がたち、いっしかこの池を,誰言う事なく『義経硯水』と、呼ぶようになった。
間も無く吹き上げの館に着くと,主の蒲原五郎範秀は大いに喜び篤く一行を,もて
なした。
.かって保元の乱に、源義朝と共に出陣した範秀は、亡き,義朝の御曹子,義経を
一目見て、感激ひとしおであった。
温かい,もてなしを受けた一行は、やっと,人心地が付いたと思いきや,義経が見
えない。
『御曹子は,いづこじゃ』家人があわてて邸内を探す。
すると義経は顔面蒼白、肩で大きく息をして厠に,倒れていた。
『いかが,なされたのじゃ、義経さま…』
名前を呼べども,返す言葉もなく、眼を,堅く閉じるのみであった。
その後も、手厚い看護をすれども気は覚めず、毎日高い熱に,うなされるばかり
である。厳しい,旅の疲れか神病みか、はた又,奇病に取り付かれたかと思い、
家人はただ,途方に暮れるのみであった。
幾日かが過ぎても、義経の病は一向に,快方へ向かう兆しはない。
家人はとうとう、源氏の氏神,正八幡大菩薩に祈るほか、術はなかった。
それから数日後、八幡大菩薩は,山伏姿に身を変え、義経の枕元に立ち寄った。
そして『冠者殿、われは都へ上る客僧なり、もしも都に知る人あらば,言伝えした
まえ、ねんごろに届けて参らせん』と言われた。
これを聞いて義経は、かすかなる息の下から『われは,義経と申す者、都より東へ
下る途中,奇病にかかり、蒲原の吹き上げの館に,臥しておりまする。矢作の宿の、
浄瑠璃御前の方へ詳しく、届けて下されたまえ』と懇願した。
言付けを聞いた,山伏は『確かに届けて参ろうぞ、よきに養生したまえ』とおうせられ、
直ちに,吹き上げの館を出立つし、瞬く間に矢作の宿に着くのであった。
その頃、浄瑠璃姫は恋の病に,沈んでいた。二度と,逢えぬやも知れぬ恋なのか。
月明かりの桜に,義経と熱く燃えた思いや、せつない胸の内を,誰に問えばよいの
かと、姫は虚ろに琴を,弾いていた。
その時、山伏に身を変えた八幡大菩薩が、姫の側により,義経の病状を伝えた。
姫は話を聞いて,驚いたが、居ても立ってもおられず、侍女の,冷泉に命じて、旅の
支度に取り掛かった。そして二人は、慣れぬ旅姿に身をやつし、矢作の宿を後に
した。浄瑠璃姫にとっては初めての、旅であった。
矢作の宿と,蒲原の吹き上げの間は、男の足ならば五日路,という道程を,九日もか
かって,歩かれた。その、か弱き足からは血が流れ、路の草葉も染まるほどである。
流す涙を道しるべとし二人は、ようようにして吹き上げの館に,着かれた。
床に伏していた義経は,もはや、屍同然であった、その姿に姫は驚き、呆然と立ち竦
んでしまう。不吉な予感を思わすかのように、空には烏が群がり,騒々しく鳴いている。
天を仰ぎ地に伏して、悲しむ姫の姿は誠に、哀れであった。
『義経様、わらわはここにおりまする、今一度,よみがえりたまえ』と、
姫は、御曹子の胸に顔をあて,泣きこがれた。すると、諸神諸仏の計らいか、
姫の落とす涙が,義経の唇を濡らすと,奇跡の薬となり,御曹子の顔に生気が,蘇って
きた。この、明るい兆しに姫は、源氏の氏神や,義経の守り神など、あらゆる神々に
深く,祈祷を行った。神々も又、哀れと思召し『いざ,われらの法力の奇特を,顕さん』と
様々な加持を御曹了に施す。すると義経は、うっすらと目を開け,微笑んだ。
その後、二十日ばかりの姫の,手厚い看護を受けると、ほどなく以前の姿に,立ち直
ったのである。
『さてさてこの度のお情け,たとえ様もない。しかし我は、東の奥州へ,下らねばならぬ。
もし、命ながらえば,明年の今頃、必ず逢いに参るぞ。せめて,形見にこれを』と,金泥
の観音経に,別れの一首を書き添えて、姫に授けた。
『移り香を、めぐり逢瀬の形見にて、君も忘るな、われも忘れじ』浄瑠璃姫はこの歌
を聞き、その場に泣き崩れてしまう。しかし、すぐに気を取り戻し,返歌をしたためた。
『逢うことも、別れることも夢の世に、かさねて辛き、袖の移り香』と,歌うと、長い黒髪
から,黄金のこうがいを抜き取り、御曽子に差し出す。
しかし、思い切れない悲しさに,姫は『いかなる野の末,山の奥までも,お供します』と、
切なく慕うのであった。
義経もまた『われも思いは,姫と同じゃ、されどこれより奥州へ,下らねばならぬ。秀衡
公に援軍を頼み、80万騎の軍勢で都へ上り、おごれる平家を,打倒せねばならないの
だ。その後必ずや、矢作の姫のところへ参るぞ。名残は尽きぬが、さらばじゃ』と、
吹き上げの館を後に、遠く奥州へ、旅立って行くのであった。
それからと言うもの、浄瑠璃姫の悲しみは,日に日に深まり、とうとう三河の国へ帰
る,気力も失せ、吹き上げの地に病で,臥してしまうのであった。
その後,十日あまりで、侍女冷泉の,必死の看護も空しく、十六歳の若き命は,朝露の
ごとく消え、御霊は浄土の世界へ,飛び去ってしまった。
美しいかった姫の、骸に里人たちはみな,涙を流した。そして、富士を仰ぐ吹き上げ
の地に、大きな塚を築き,姫の供養をするのであった。塚には目印となる、松の苗木
が,六本,植えられた。
姫の思いか,天の情けか、松は見事な大樹に成長し、いっしか『六本松』と,名付けら
れた。その後、里の人々にも親しまれ、また,富士川から都へ上る旅人のよき,道しる
べになったという。
明治31年、時の町長,五十嵐重兵衛の手で、この吹き上げの地に、浄瑠璃姫の墓の
碑が,建立された。
『語り継ぎ、言い継ぎつつ今になお、いくりの人の袖を、濡らすらん』
と、碑面に彫られた哀愁の歌が、今なお多くの人々に,伝えられている。


浄瑠璃姫の墓 吹き上げの六本松
(蒲原町蒲原中学校前にあります)
![]()

<静岡県東海道四百年祭公演>


岡崎城能楽堂公演リンク<H14年10月27日(日)>
![]()

原 作 蒲原町文化財保護審議会会長 塩坂高男
脚 本 津軽三味線白井勝文
三味線弾き語りコーナーへは、下記のナビゲーションからどうぞ |