三味線弾き語りコーナーへは、下記のナビゲーションからどうぞ
|
平 敦 盛
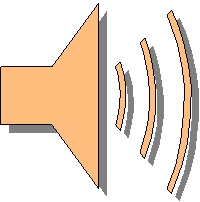
原作 山本ちよ 仕上 白井勝文
![]()
青葉の笛
花の次郎長三人衆
ああ梶原景時公
ああ信康
今は昔。平家にあらざるは人にあらずと、栄華を極めた平家も、
満つれば欠けるの例のとうり滅びの道を、たどり始めた頃のこと。
ときは寿永三年(西暦一一八四年)二月七日。
一ノ谷の合戦で、追い詰められた平家は最後の砦、一ノ谷の城にたてこもった。
源氏の義経や、範頼の軍に囲まれながらもなお、平家一門の侍達は、笛や
ひちりきで別れの宴を催していた。
朝廷に仕える、貴族にならっての風雅なしきたりを、身につけていたのである。
そのとき、無官の大夫といわれる若き公達、平敦盛が人々の賞賛を浴びていた。
「お見事。敦盛様の横笛はひとしお、心に響く音色でござるなあ〜。鳥羽院から、
賜ったという『小枝』 を、吹きこなしておられる」
「やはり、お血筋というものでござろうぞ。三代続いた笛の、名手であられるからのう」
敦盛は、人々の言葉に軽く目を伏せ、涼やかな笑顔で一曲吹き終わり、さりげなく
笛を置く。その日のご装束、梅の匂いの肌寄に、唐紅の上衣を召されいつになく、
華やかであった。
間もなく、非常な命令がくだされた。
「方々に申し上げる。我々は遂に三方を敵に囲まれたもはや、逃れる道はただ
一つ、海へ出る他はない、海辺に助け船が待っておる急がれよ」
雅にひたっていた平家の武将達も、いざとなってはわれ先にと、城を捨てるに
急ぐ。敦盛も城を出た。
馬の手綱を手にした時ふと片手を、鎧の引き合わせに当てた。
「無い!」肩を落として、「ふっー」と息を吐く。
「なんとしたことぞこの敦盛、笛を忘れるとは。『小枝』を置き去りにしたと
あっては平家一門の名がすたる」と低く呟いて、ひき返した。
宴の後の侘びしい窓辺にひそと置かれた笛を手にとり、敦盛は急ぎ城を出た。
この『小枝』は、『蝉折れ』と共にかつて、鳥羽院が秘蔵していた、天下に
二管の名笛ありと、言われた横笛である。この由緒ある小枝を敦盛は、笛に
優れたる故若くして、継承したのである。
敦盛は馬を跳ばして浜辺へ出た。平家の武将達をのせた御座船は、浜辺を離れ、
沖の波間に漂っている。
「あ〜っ、束の間の遅れが我を離したか」
敦盛は沖の船を見つめ、唇を噛んだ。
命よりも笛を大事に思えばこその、遅れであった。
平家の誇りを守るが故か、敦盛ここで運命が別れた。
御座船を追っても遅かりしと、思いながらも敦盛は、渚に沿って馬を走らせる。
戦い済んだ浜辺、折りしも、武蔵の国の荒武者、熊谷直実が何事か、つぶやき
ながら馬を進めていた。
「一ノ谷の戦で先陣を志したものの、なにほどの手柄をあげることもできず無念、
このうえなしじゃ、もしここに、敵が現れたなら首を獲りたいものよ」
そんな荒武者の独り言も、うち寄せる波のざわめきが、かき消すだけであった。
だが、ふと目をやれば、平家の侍大将が、御座船に向かって行くではないか。
その身なりは、萌黄匂の鎧着て、鍬形兜の緒をしめ、練貫に鶴の刺繍の直垂と、
贅を尽くした装束である。
「お、これは大物」わが思い天に通じたるかと熊谷は、手綱を握り直して叫んだ。
「そこへいかれるは平家の、御大将と見受けたり、敵に背を見せるとは卑怯であるぞ、
ご勝負あれ」

敦盛、ううっと、呻いてふりかえる。
願い叶ったりと熊谷、勝ち戦の勢いにのって強気に迫る。
「あの船までは波荒く馬も、泳ぎかねて見えまするぞ。引っ返して御勝負あれい。
さもなくば弓矢にて、勝負いたさん」
「なにを申すか、源氏の赤錆びた矢に討たれたとあっては、平家一門の名が廃る、
我が、この矢を受けてみよいざ、勝負!」
馬上から弓を構えれば錦の脛当てに波しぶきが飛び、黄金作りの太刀が光る。
敦盛は若さにまかせて、フィツ、フィツ、フィツと、間断なく矢を放つ。
さらりと受け流す熊谷、起き直って打ち返す。
二の矢、三の矢と次々と射るが、勝負がつかない、とうとう、手柄を焦る熊谷は
叫んだ。
「寄れっ、組んで戦わん」 「心得たり」
今度は互いに弓矢を捨て馬を、取っ組み合うほどまでに近づける。
鎧の袖を引っ違えムンズと、組み合う二人は二頭の馬の間に、ドッドと落ちた。
いたわしや敦盛。気持ちばかりが勇んでも、百戦練磨の荒武者熊谷には到底、
太刀打ちできぬやすやすと、取り押さえられてしまう。
熊谷はしてやったりと刀を抜き、敦盛の首筋に当てた。
その時、胸元から、焚き染めた香の香りが漂うのを不審に思い、兜をあげて顔を見た。
熊谷の手がふるえる。 「やや、ここ、これは、なんと…」
薄化粧にお歯黒、額に描いた太い眉いかにも、高貴な若武者である。
齢の頃は十六か七か、氏素性のよさを芯からとき放つ美少年の顔がそこにある。
我が子直家とは同じ年頃、あまりの労しさに押さえ付けた手を、わずかにゆるめた
熊谷。目を見開いて息を飲む。敵とはいえ敵にはならぬ、その姿あ〜〜。
「さてさて、いかなるご公達にあられるや御名を、名乗り給え」
「そなたは誰ぞ」
「人並みに、数えるほどの者ではありませぬが、武蔵の国の住人、熊谷の次郎
直実と申す」
「さて我は、名乗るまい。この首をとりてそなたの主人義経に見せよ知ってお
ろうぞ、もしも見知らぬならば、範頼に聞け、それでも知らぬとあらば、
名もなき者として草むらにでも捨て置け」
敦盛は組み敷かれたままグッと睨んだ。
功名心と情けの、情にからまれる熊谷、目をしばたいて説きふせる。
「さても武士とは、哀しきものよ。主君のためには親と争い子と戦い、
はからざる罪をつくるのが我ら、武士のならいでござる。こ度の戦で
熊谷と出会いたることも前世からの、因縁と言うものであろうぞ、
せめて、後の菩提を弔うほどにさあ、名乗られよ」
「なに、菩提の供養とな。それほどまで、思ってくれるのであれば、
名乗るまいと思うたが、名乗って聞かせようぞ」
熊谷は押さえつけた腕を離し、座り直した。
改めて見れば幼さを、残した頬が丸みを描き、上品な薄い唇を口惜しげに
キリッと結んでいる。
敦盛は波打ち際に毅然と構える、今や、戦うすべなしとはいえ、平家の一軍
を率いる御大将。誇らしげに胸をはって言った。
「我は修理太夫、経盛の三男、ゆえに清盛公は伯父御にあたる未だ、
官職なきゆえ名は誰いうとなく、無官の大夫敦盛とよばれておる。
生年は十六歳口惜しくも戦はこれが、初陣である。このような目に遭うのも、
運命というものであろうさっ、早ように首を打て」
「さすれば御身は、桓武天皇の末裔であられるかそれに、御歳十六歳とな
我が子直家と同年であるか。歳を知ればなお更のこと、我が子に思えてならぬ。
この熊谷もはや御身を打つこと、かないませぬ、さっ、お助け申すほどに
早う、逃げられよ。」
と、言いながらも辺りを見回せば、遠く近く、義経軍、範頼軍が取り囲み、
敵の大将を捕らえた熊谷の、成敗いかにと固唾をのんで、見張っている。
風にのって味方の声も、流れてきた。
「さては、敵を捕らえても動かざるは、助けるに違いない、熊谷は二心ある様子。
ええい、場合によっては熊谷ともども、討ち取れ〜い」
「いかん!このままでは二人とも、討ち取られてしまう」
あなたこなたの情勢から熊谷は、遠くで見守る兵達を顎で示し敦盛に、
覚悟せまる。
「先に見えるは我が味方の軍勢われが、助けたとしても御身はもはや、
逃げられますまい。
あの者達の手にかかるよりはこの、熊谷の手で討たれよ必ずや、
後後の世まで弔うほどに」
敦盛はかすかに頷き、背筋をただして目を閉じたその、静かなるさま
深山の泉の如し。
だが、我が子と同じ歳の公達を討たねばならぬ、荒武者熊谷の心は
かき乱れる。
「如何にして若い御身がこのように、落ち着き払っておられるのか」
「我は戦など好かぬ、醜いこの世の争いなど見とうはない。勝った敗けた
と言うても所詮、この世のたわごと、例え栄華を極めようとも
人間たかだか五十年のいのち、生を受け滅せぬ者あろうか。
武人の誇りを持ちて、常しえに旅立つ我が心は無にして、静かであるぞ」
悟りきった敦盛の言葉にグサッと、胸を突かれた熊谷は肩をおとす。
「この場に及びそこまでの、悟りの境地を得ているとは敵ながら、
天晴れであるぞ」
覚悟した敦盛は目を閉じ、心の中で噛み締めるように呟いた。
<我はまだ名笛、小枝にふさわしい音色で、曲を奏でてはおらぬ。
あの世とやらで、これぞ敦盛と言われる笛を、極めようぞ>
敦盛の口元がわずかに、ゆるみ心は既にここにあらず。
その時、「ごめんっ」と、祈るがごときひと言。
ブシィッ! と振り切った熊谷の、一刀のもと平敦盛は、討たれた。
水面にゆれる月影のように、短い一世ではあったが敦盛は平家の、
名誉と誇りを守り通した。
ふと、鮮血に染まる亡骸を見ると、鎧の裏に秘められた横笛が、目に入る。
「さては、一ノ谷の戦のあと、砦から洩れ聞こえたる笛の遠音はこの、
公達の吹く笛であったのかせめて、この笛をお手に握られよ」
物言わぬ、敦盛の手に取らせると、熊谷の目から初めて、涙がこぼれた。
時立たずして熊谷は、数々の命をあやめた弓を折り、弔いの旅にでた。
武人の誇りを貫き通し、はかなく消えた敦盛を偲べば熊谷の、
心の乱れも静まり、安らかな境地となるのであった。
その後、法然上人を師匠と仰ぎ、元結いを切り落としその名を、蓮生房と改めた。
人間五十年、化天のうちに比ぶれば夢幻のごとくなり、ひと度生をうけ滅せぬ者、
あるべきか。
関東の荒武者、熊谷直実を、悟りの境地へ導くほどの凛々しく潔い、
敦盛の最期であった。
武人の誇りと名誉を貫きり通した敦盛に対し、荒武者熊谷直実の武勇もさることながら、
人情の篤さも人後に落ちぬ、武士の情けと弔いの情は、清々しさとして大和魂に響いてくる。
特に最後の「この笛をお手に握られよ」の言葉は、物語を織り成す二人の情感の締めくくりとして、
涙を誘う最高の台詞である。
学校での道徳講演で、平敦盛を弾き語りを行い
人に対する思いやりの美しさを鑑賞しました。
.jpg)
藤枝市熊谷山蓮生寺にて 台本制作者山本ちよ
蓮生寺の裏にある蓮花寺池、この池の名も蓮生坊に
因んで付けられたのではないだろうか。
三味線弾き語りコーナーへは、下記のナビゲーションからどうぞ |